日本では早ければ来年7月に新日本円札が発行されます
日本の財務省と日銀は、早ければ来年7月にも日本円の新札を発行すると発表しました。
日本の新紙幣の肖像には、世界で初めて「ホログラフィー(Holography)」という技術が採用されており、偽造防止の効果が高まるだけでなく、肖像がより立体的に見えるようになっています。
現行の紙幣は新しい紙幣が流通した後も引き続き使用されます。

日本銀行本店(本店)です


新1万円札の表には、江戸時代末期から大正時代にかけての大実業家、渋沢栄一が描かれています。「日本企業の父」、「日本の金融王」、「日本近代経済のリーダー」、「日本資本主義の父」、「日本近代実業界の父」などの冠を持っています。渋沢栄一が書いた『論語と算盤』という本の中に、道徳経済の統合という考え方があります。幼年期に学んだ論語(倫理道徳を表す)と商売で使う算盤(経済を表す)は矛盾関係にあるのではなく、経済の発展を追求するのは個人の利益を独占するためではなく、国家全体の発展のためであり、社会全体から得た利益は再び社会に還元すべきだと考えたのです。強いて富の根源を問えば仁義道徳だと書いています。正しい道理の下で豊かになれば,その豊かさは永遠に続きます
アメリカの経営学の専門家であるピーター・ドラッカーは、20世紀に日本が世界的な経済大国になるには、渋沢栄一の思想と業績に大きな影響があると評価しています。
新1万円札の里に印刷された東京駅丸の内側の改札口です。


新五千円札の表は、明治時代の教育者であり、日本女子教育の先駆者として日本女性の地位向上に大きく貢献した津田梅子が1900年に創立した女子英学塾、すなわち津田塾大学の前身です。
新5000円札の裏面に印刷されている多花藤(たかはなふじ、学名:Wisteria floribunda)は、マメ科藤属の植物です。日本および中国各地で栽培されている中国原産の植物です。


新1000円札の表は、日本の医学者で細菌学者の北里柴三郎さんです。彼は破傷風の治療法を開発し、日本の近代医学の基礎を築いた有名な微生物学者です。
北里は、私立感染症研究所(現・東京大学医科学研究所)、土筆岡養生園(現・北里大学北里研究所病院)、私立北里研究所(現・学校法人北里研究所)の創設者でもあります。また、北里大学学祖、慶応義塾大学医学科(現・慶応義塾大学医学部)創設者兼初代課長、慶応義塾大学病院初代院長、日本医師会創設者兼初代会長も務めました。
「神奈川沖浪裏」は、浮世絵画家・葛飾北斎が1831年から1833年にかけて出版した、富嶽三十六景シリーズの木版画です。出版当時は数千点が製作されましたが、現存するのは数百点と推定され、大英博物館、メトロポリタン美術館、東京国立博物館などの大博物館にも一部が所蔵されています。

円札は国立印刷局が印刷しています。写真は東京工場
2000円札は使用量が少ないため、デザインはありません。実は2003年に最後の新紙幣が日本銀行に納入されて以来、国立印刷局は2000元紙幣を印刷していません。
日本の各都道府県の統計の中で、沖縄県は2000円札の使用率が最も高い1つです。表に沖縄県のシンボルである守礼門が印刷されているため、県民の2000円札の受け入れ度が高いです。近年沖縄県は観光促進のために2000円札の利用を促進しており、2000円札対応のATMや自動販売機の設置を企業や団体に奨励したり、2000円札利用者を対象とした各種抽選会を開催したりしています。


現在、円は国際通貨の中では、ドル、ユーロに次ぐ第3位の取引量です。

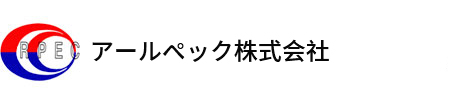



 huantai@qdhuantai.net
huantai@qdhuantai.net  日本国名古屋市天白区元植田1-2101 GRACE植田308
日本国名古屋市天白区元植田1-2101 GRACE植田308 

